防災講座資料ダウンロードページ

ようこそ ママキャン!ブログへ
防災講座に関する情報はこちらのページからご覧いただけます

免責:このページの閲覧に起因する損害、損失に対して、製作者は一切の責任を負いません。全て利用者の自己責任に基づいて行ってください。
ダウンロード一覧
「防災カード」PDFデータ
「防災カード」PDFデータ無料ダウンロード(新しいページが開きます)
A4サイズで1枚にクレジットカードサイズの防災カード2部印刷できます。
普段は、防災ポーチやお財布など、個人情報を盗まれにくい場所に入れて携帯してください。
名札ケースに入れて避難リュックの名札にすることもできます。
(避難リュックは紛失防止のため、名札を付けておくことを推奨します)
「防災カード」と合わせて印刷したい「171ポケットガイド」
「防災カード」の情報をもとに、家族の電話番号を使って、「災害伝言ダイヤル171(いない)」を使う方法は、NTTよりカード印刷用のPDFが無料で公開されていますので、以下をご参照ください。
NTT東日本版
https://www.ntt-east.co.jp/saigai/movie/pdf/pocket_pc.pdf
https://www.ntt-east.co.jp/saigai/voice171/images/171pamphletquick.pdf
NTT西日本版
https://www.ntt-west.co.jp/dengon/pdf/171manual.pdf
防災講座 配布プリント資料①②③ PDFデータ
防災講座 配布プリント資料①②③一括ダウンロード(64.9M)
防災講座 スライド閲覧用PDF
講座の復習でオススメしたいコンテンツ
どんな備え、行動が、内閣府で推奨されているのかも見てみましょう
防災士になりませんか?
全国最年少の防災士は、なんと小学2年生!
防災士の資格を取るのは難しくはありません。
また防災士の資格があるからといって、なんらかの義務や参加の責任は伴いません。自由参加です。
あなたも防災士の資格を取って、地元の防災士の会に参加してみませんか?
わたくしママキャン!も2023年12月に防災士の資格を取得しましたが、家庭優先のため、防災士としての活動はあくまで自分の時間が取れる時のみです。
また、災害時も同様、必ずしも防災士として自分が現場で活動できるかというと、私が不在になると他に子供の面倒を見てくれる人がいないため、できる活動の範囲は非常に狭くなっています。
そういう、忙しくて、個人の活動が思うようにいかない人でも、より多くの防災士が協力しあって、その時々の欠席者の穴埋めをしあって、個人の力に頼らず、地域の組織力を高めて防災に取り組み、また次の世代へと引き継ぎを行うのが、良い流れなのではないかと考えています。
防災士になるためには、まずお住まいの自治体のHPや市役所などで、資格取得についてご相談ください。だいたい1年に1度、2日間の研修を受け、それほど難易度の高くない試験を通れば資格が取得できます。取得するのに教材費込みで1万円しない程度のお金がかかりますが、自治体で使える補助がないか確認してください。
Yahoo!防災速報 スマホアプリ

リアルタイムの災害情報、ハザードマップ、避難所マップ、防災手帳など、防災に役立つ情報が集約されています。ぜひ活用してください
ペット防災について 参考例:日本レスキュー協会
災害への備え | 認定NPO法人 日本レスキュー協会
https://www.japan-rescue.com/%e5%8b%95%e7%89%a9%e7%a6%8f%e7%a5%89%e3%83%bb%e4%bf%9d%e8%ad%b7%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/disaster-control/
発災時、迅速に支援に繋がる体制作りを構築したい!
https://www.furusato-tax.jp/gcf/2883
ペットを飼っている方は、自分のペットの備えを行うことはもちろん、災害時にペットを一時預かりしてくださるボランティア団体さんや、NPO活動団体さんらに、日頃から寄付をし、ボランティアとしての参加をされるのがオススメです。
こういう活動をなさってくださっている団体さんが減ったり資金不足に陥れば、いざという時、自分のペットを預ける先が見つからずに苦労すると思います。
日本レスキュー協会さん以外にも、ペットの一時預かりなどの各ボランティア団体が地域ごとに活動されており、自分が関われる範囲で普段から顔の見える付き合いを続けていくことが、自助・公助へのスムーズな繋がり作りになります。
防災士のためのYoutube防災講座 講座資料
実施要領の記入されたパワーポイント
防災講座②の台本が入ったパワーポイント(183M)
(データサイズが大きいため、wifi環境でダウンロードしてください)
内容は公演者が扱いやすいように自由に改変してください
改変した場合は、クレジットに 改変者:日付@改変者名 を追加してください)
講座内で引用している動画
講座前に、このページを開いたブラウザを、プロジェクター投影画面にあらかじめセットし、フルスクリーンモードにて再生可能かをチェックしてください。
サウンドが会場に十分な音量で流れるように調整してください
講座①内で引用している動画①地震 最初の1分〜3分
講座①内で引用している動画②津波 開始位置3:37〜4:23
講座①内で引用している動画③土砂災害 開始位置1:16〜4:32
講座①内で引用 学区マップ
講座①内で引用 学区マップに重ねられるハザードマップ
※尺度を調整し、スクリーンショットを撮ったものを、自分で画像処理して重ね合わせています
もし、その作業が難しければ、講座を行う市町村のハザードマップから、
- 学区周辺のハザードマップ、
- 生徒や親御さんの生活圏でもっとも親しみのある、危険なエリアのハザードマップ
の2種を切り出して、パワーポイントの当該ページ画像を差し替えてください
ママキャン!流 防災ポーチ、避難リュック 詳細
ご注意:あくまで、ママキャン!流の紹介です。
人により、状況により、必要なアイテムは変わります。
本サイトを参考されたことによる問題には一切責任が負えませんので、全て自己責任にてご参照ください。
参考の100均アイテムがお店になければ、オンラインで注文できる他、お店の人に商品のJANコードを伝えて注文することも可能です。
ネット注文するときは、周りのお友達と声を掛け合って、一括共同購入すれば、送料無料ラインに乗せやすいと思います。
小学生用、最小防災ポーチ紹介
- 防災カード(印刷代のみ)
- 蓄光ホイッスル(キャンドゥ110円)
- コンパクトレインコート子供用(ダイソー110円)
or コンパクトレインコート大人用(ダイソー110円) - ライト付き防犯ブザー(ダイソー110円)
or ヘッドライト(キャンドゥ110円) - 絆創膏
- ゴミ袋と輪ゴム(30リットルのゴミ袋2枚、アイラップ2枚、輪ゴム4本)
- 防災ポーチの入れ物(B7サイズ)(ダイソー110円)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
購入金額合計 440円プラスα(全体で100g程度)
数ある100均商品の中で、現在もっともおすすめの商品構成です。
兄妹分揃えたとしても、それほど家計の負担にならないかなと思いますが、いかがでしょうか。。
小学生用、避難リュック詳細
- リュック・エコバッグ、外付けキーホルダー、名札(小計約890円)
- リュック(キャンドゥ330円)(製造終了品のようです。売り場でみかけたらラッキー)+ 肩ひもベルト(ダイソー110円)
- 肩がけできるエコバッグ(セリア110円)(セリアにはオンラインショップは無いため売り場で探してみてください)
or 背負えるナップサック型エコバッグ(ダイソー110円) - 内側に入れる防水用のゴミ袋(45ℓ1枚約10円)
- 防災カード(印刷代のみ)
- 名札ケース(ダイソー2個入り110円)
- ライト付き防犯ブザー(ダイソー110円)
- 蓄光ホイッスル(キャンドゥ110円)
- 避難リュック用防災ポーチ(小計約2,000円+α)

- 避難リュック用の防災ポーチの入れ物(ダイソー)110円
- ヘッドライト(キャンドゥ110円)
- ヘッドライト用電池(ワッツ110円)
- ヘッドライトの電池交換用のドライバー(セットのうちマイナス1本のみ使用)
- コンパクトレインコート子供用(ダイソー110円)
or コンパクトレインコート大人用(ダイソー110円) - 絆創膏
- 常備薬・予備のメガネ
- アルミブランケット(ダイソー110円)
- 171の使い方カード(印刷代のみ)
- 簡易トイレ (ダイソー110円)
- ティッシュ&除菌ウェットティッシュ
- 小銭(100円玉、50円玉、10円玉を3枚づつくらい)
- 家族の写真
- 爪切り、カッター、とげぬき
- のど飴、塩分タブレット
- マスク1枚(できれば防塵用がベター)
- 水、食べ物、おやつ(子供が好きなものを)(小計約520円)
- 水500ml
- ひだまりパン(子供が食べやすい非常食の例)
- 氷砂糖(賞味期限を気にしなくてOKなおやつ)
- 塩分補給タブレット、カロリーメイト、えいようかん、カンパン、ライスクッキーなど、調理しなくてもすぐ食べられるものであれば何でもOK
- 上着、帽子、手袋(小計約330円+服とクツレインカバー)
- ウィンドブレーカー(軽くてたたむと小さくなる薄いもの:親戚のおさがり)
- 帽子(ダイソー220円)
- 手袋(ダイソー110円)
- 長靴orくつカバー(セリア110円でも売っていますが、靴の裏が滑り止め付きでしっかりしたものだと安心です)
- 着替え、サンダル(小計約110円+服)
- 上下の服(夏でもできるだけ長袖、長ズボン:友達のおさがり)
- 下着、靴下、肌着(しまむらでまとめ買い)
- サンダル(ダイソー110円 スリッパでも良いですが、できれば外でも使える底が防水で厚みのあるゴムのもののほうがオススメ)
- もしあれば、運動部などで使う撥水タイプのジャージがあると汚れが落としやすく中に着ている服が汚れるのを防げます(親戚のおさがりを活用中です)
- ジップロックの袋(入れ物)
- タオル、体拭き(小計約110円+タオル)
- タオル(頂き物とかのフェイスタオルで良いと思います)
- 体拭きウェットティッシュ(ダイソー110円 備蓄用ウェットボディタオル)
- 文房具、ガムテープ(小計約660円)
- はさみ(セーフティー携帯ミニはさみ だと子供が怪我しにくいと思います)(ダイソー110円)
- 耐水メモ帳(ダイソー110円)
- 油性マジック(黒、赤など、ツインタイプだとなお良)(ダイソー110円)
- 多機能ボールペン(4色ボールペン+シャープペン)(ダイソー110円)
- 黄色いビニールテープ(ダイソー3つ入り110円)(粘着テープでも良いと思います、ビニールテープは粘着力が弱いので、遊ぶのにも使いやすいです)
- 黒以外の文字の書ける色のダクトテープ(キャンドゥ110円 服の補修などにも使えます)
- 衛生用品、ゴミ袋(小計約110円+消耗品新しく買えば1500円ほど)
- 予備のマスク
- 予備のティッシュ
- 予備の除菌ウェットティッシュ
- コップ付き歯ブラシ(ワッツ110円)(個人的にコップ付きがおすすめ)
- 生理用品(ちょっと値段は高いけど薄いタイプ3日分程度あると良いです)
- 割り箸、スプーン、紙皿(スーパーやコンビニでもらったもののストックから。重さに余裕があればプラスチック製のほうが便利かも)
- ビニール袋(家にある大きめのゴミ袋、黒いゴミ袋、アイラップ、輪ゴム)
- 季節の追加品(小計 夏約330円 冬約330円+服)
- その他(全て買ったら1,540円+ゲーム機代)
- アイマスク(トラベル小物セットでもOKだけど、つけ心地の良し悪しまで気にする人はつけてみて一度寝れるかどうかお試しいただくほうが良いと思います)
- 耳栓(ダイソー110円)
- エアークッション (ダイソーの防災用エアークッションは使い捨てなので、キャンドゥやワッツの使い捨てでないクッションのほうが個人的には好きです)
- 電池のいらないライト(ダイソー 24時間タイプ110円 72時間タイプ 220円)
- ラジオ(イヤホン、電池も。以前はワッツで880円で売っていましたが売り切れのようなので、Amazonより。充電式より電池式、多機能より単機能のほうが個人的にオススメです。軽さは正義!)
- トランプ(遊び道具、UNOなどでも良いと思います。もし台風などで時間的に余裕のある避難だったら、人生ゲームとか色々持っていっても良いですね。)(ダイソー110円)
- アルミクッションシート(ダイソー110円 かさばりますが、冬の場合は持っていくと、床からの冷気が多少抑えられます。車避難などで余裕がある場合はサバイバルシートやエアーマット、寝袋も持っていけると良いでしょう。防災用寝具のおすすめはそのうち自分が試したものを動画にしようと思います)
- 新聞紙(敷いても良し、燃やしても良し、吸わせても良し。最近は新聞を取っている家も少ないと思いますが、親戚まわりからいただいたり、許可を得て廃品回収でもらっておくと、無料なお役立ちアイテムとして活躍します)
- 自治体で配っているハザードマップ(市役所で無料でもらえるはずです。市役所のHPなどからダウンロードして印刷も可能だと思いますが、個人的にはスマホが使えるならYahoo!の防災アプリが一番早い気がします。紙の地図は保険にあるほうが良いですね)
- ゲーム機(電気は比較的復旧が早いと言われているので、switchやipadも充電器と一緒に持っていってあげると、長期滞在になっても子供が退屈せずに済むと思います。ちゃんと毎日運動もさせてあげたいところです)
その他:蓄光アイテム、反射板類を取り入れて、より発見しやすい、発見されやすい防災アイテムにしよう(2〜300円)
私はリュックには反射テープ、枕元用の防災ポーチには蓄光キーホルダーを付けています。(キャンドゥの蓄光キーホルダーは売り切れてしまいましたが、ダイソーやセリアで売っている蓄光パウダーなどで自作できます。実験してみましたが光り方も同じ程度でした)
ママキャン流小学生用避難リュック 予算概算:5,060〜9,310円+服&ゲーム機
ほぼ100均で揃えても、結構な金額がかかっていました。
ウチはできる限り、おさがりを上の世代から下の世代へ引き継いでもらったりして、小学1〜6年までの間、消耗品の取り替えをしながら保管していこうと思います。
食べ物、飲み物はほぼ取り替える必要のないパンや消費期限の無い氷砂糖と水ですが、2年に1回は服のサイズをあげていかないといけませんね、子供の服はサイクルが早いので中古です。
ママキャン!より愛を込めて
日々の暮らしで余裕がなくて、とてもじゃないけど、防災ポーチも避難リュックも作っていられない。そういうご家庭もあると思います。
大丈夫です。
もし出来たら、自治体のHPのハザードマップをご覧になって、手書きのメモで「防災カード」を作って、家族と待ち合わせ場所を約束しておく、ここまで出来たら100点満点です!
もし出来なくても、これを読んでる時点で素晴らしい!頑張ってます!えらい!
災害は確かにいつ起きるかわからないし、災害時には備えがあるのと無いのとで多少の差も生じるかもしれませんが、自分が備えられなくても、周りの多くの人が備えることによって、お店で買えるものが増えたり、配給の余裕が増えたり、レスキュー隊や自衛隊の方達の動きがスムーズになって、全体的に助かる人が増えていくと思います。
実際の災害時、被害に遭うかどうかはほとんどが運次第だと思います。
n=1の確率論で見れば、たまたま自分の住んでいる地域が、自分の生きている間に災害が生じなければ0%、たまたま災害が発生すれば100%の確率です。
日々、怯えて暮らしたり、防災のことで焦って暮らすよりかは、美味しいものを食べて、毎日しっかり寝ることのほうが大事ですから、私の発信する情報も含めて、防災のトレンドを気に病まないでくださいね。
こんなことを書いてる私だって、どん底の時には防災のことなんて気にしてる余裕もなく、ひたすら寝ていますから(笑)
人間の死ぬ確率は100%です!
ご注意:都会の被災と、田舎の被災では、ベースとなる条件が違う
今回の講座は、日本の地方都市や田舎の小学校での授業を想定しています。
大都市では、災害発生後の避難やサバイバルのロジックが変わってくるため、この講座の内容は当てはまりにくいかもしれません。
私は2011年、東日本大震災の時、東京に住んでいました。
震災直後には、全ての店から商品は消えて、輪番停電が始まり、原発事故の影響も懸念される中、ペット(猫2匹)を連れて自主避難を行い、現在は田舎に移住して15年になります。
単身、健康であれば、大都市での災害でも身軽に避難できるかもしれません。しかし、子供がいる、ペットがいる、自分自身が高齢となり体力の衰えがある、という条件では、都市部での災害後のサバイバルを乗り越えられる自信が私にはありません。
日本の田舎は人口減で、どこも空き家だらけ、限界集落だらけです。
子育て世代が、地方に分散することは、日本政府も推奨する、減災の方向性です。
地方には若い人の仕事が無いので、すぐに移住できる人が増えることは無いと思います。私自身、都会でやっていた仕事を諦め、田舎にたまたま実家があったので、そこを拠点に移住を行いました。
今後予想される大都市部での巨大地震、火山の噴火、大規模火災などでは、多くの死者が出る予想がされています。
田舎の方が災害が軽く済む、という話ではなく、人口が集中している場所ほど、一度に被災する被災者の数も膨大になるため、周辺地域からの救助などのリソースが数的に間に合わないという予想があります。
そのため、究極的に、日本全体での減災を目指すのであれば、なるべく、人口密集地域から、地方移住が進んでいくのが望ましいでしょう。
私には、大都市部向けの防災講座を作るだけの知識、経験がありません。
都市防災は都市防災の専門家の方による発信をお待ちしています。
防災講座 → 防災キャンプへ 繋げていきたい
防災講座で学んだことを実践し身につけるため、実際に子供が自分で作った避難リュックを持ち込んでの、防災キャンプ体験へ、ステップアップができると良いなと思います。
体験は希望者のみ、小学1〜6年生とその親、夏休み期間などが良いかと思います。
怪我や事故などの防止策、活動資金の捻出、参加する子供の数に見合う十分な運営スタッフの確保など、課題は大きいです。
体験から学びを得た子供たちが、大人になった時、次の世代の防災士として、地域で活動してくれるようになるのが夢です。
そのためには、まず防災キャンプの指導員ができるレベルの防災士に自分自身がステップアップしていかなければなりませんね。頑張ります!そして楽しみます!
地域防災×子供 日本は防災の授業を義務教育に取り入れても良い
動画内でもお話しましたが、子供達への防災の啓蒙活動は、地域全体の防災力をアップする貴重な機会だと思います。
私が理想と思う、子供達への防災ステップはこんな感じです。
・未就学児3歳〜6歳 体を使って楽しむ防災体験
(揺れてる時はダンゴムシ、揺れていない時は走らずで、誰が一番早く避難場所につけるか競争、防災ピクトグラムかるた、など)
・小学生 防災基礎知識を理解しながらの避難訓練
(本講座を学年に合わせてカスタマイズ)
・中学生 自分で考え行動
(マイタイムライン作成や避難所運営シミュレーション)
・高校生 自分たちが作る防災レジーム
(自分たちの地域には、どんな防災が必要か、フィールドワークで調査し発表)
・大学生 プレ防災士としての地域防災イベント活動参加
(政治家との語らい、大学名での研究発表、国内外との情報交換)
学校外:地域の避難訓練、防災イベント、防災キャンプ、で地域の人との交流、家庭の防災
子供達を通して、その親、祖父母、兄弟への啓蒙と地域活動との繋がり作りを行い、災害発生時に、すべての人がそれぞれの立場により、スムーズな役割分担ができるように組織化が進んで行くと良いなと思います。
全国の学校が一律な教育を行うのは、許可や手続き関係に時間がかかると思いますが、一般人である防災士が招かれて行う課外事業でしたら、かなり自由な内容でも許されると思いますし、時代の変化に合わせて柔軟にスピーディに対応できるかと思います。
各地元の防災士さんの活躍が期待されます。
 |

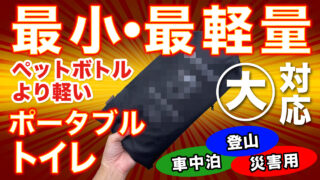
































コメント